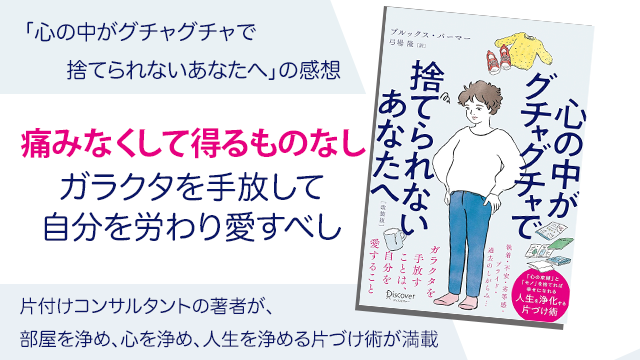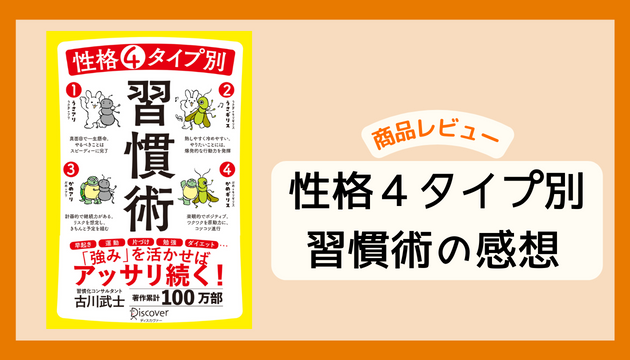『東京物語』感想|なぜ今、小津安二郎の映画が心に沁みるのか

なぜ今『東京物語』を観たのか
『東京物語』というタイトルは、以前から知っていました。
名作として語られる映画だということも。
ただ正直に言うと、
「古い映画だし、きっと私にはわからない」
どこかでそう決めつけていた作品でもありました。
そんな私がこの映画を観るきっかけになったのは、
断捨離提唱者・やましたひでこさんのYouTubeでした。
禅と断捨離についての対談動画の中で、
文芸評論家の浜崎洋介さんが
「禅・断捨離・日本人の美意識」という視点から
映画『パーフェクト・デイズ』について語っていたのです。
その中で紹介されていたのが、
『パーフェクト・デイズ』を撮ったドイツ人監督が、
小津安二郎監督の作品、とりわけ
『東京物語』に
深い影響を受けているという話でした。
老夫婦のお父さんの、あのシンプルな暮らし方に
心を打たれたのだそうです。
さらに印象的だったのは、
小津監督作品に数多く登場する笠智衆さんの役名が
「平山」であることにちなんで、
『パーフェクト・デイズ』の主人公にも
「平山」という名前が与えられている、というエピソードでした。
国も文化も違うドイツ人監督が、
そこまで敬意を込めて小津作品と向き合っている。
それを知ったとき、
「ドイツ人の心にまで刺さる『東京物語』とは、
一体どんな映画なのだろう?」
と、強く興味を惹かれました。
禅や断捨離、日本人の美意識とつながる作品なら、
今の自分だからこそ受け取れるものがあるかもしれない。
そう思い、Amazonプライムで『東京物語』を観ました。
『東京物語』のあらすじと時代背景
『東京物語』は、1953年に公開された
小津安二郎監督の作品です。
舞台は、戦後まもない日本。
高度経済成長が本格化する少し前の、
まだ人々の暮らしに余白と静けさが残っていた時代です。
物語は、広島・尾道に暮らす老夫婦が、
東京で暮らす子どもたちを訪ねて上京するところから始まります。
長男は医師として、長女は美容師として、
それぞれ家庭と仕事を持ち、忙しい日々を送っています。
一方、次男は戦争で亡くなっており、
その妻・紀子だけが「家族ではない存在」として登場します。
それでも彼女は、義父母を気遣い、
時間をつくって寄り添おうとする数少ない人物でした。
東京に出てきた老夫婦は、
久しぶりに子どもたちと会えることを楽しみにしていましたが、
実際には、仕事や家庭に追われる子どもたちから
十分にもてなしてもらえるわけではありません。
悪意があるわけではなく、
ただ、それぞれが自分の生活で精一杯なのです。
やがて老夫婦は尾道へ戻り、
その後、母親が体調を崩して亡くなります。
葬儀のために再び家族が集まりますが、
そこで描かれるのもまた、
誰かが悪いわけではない、
けれど少し噛み合わない家族の姿でした。
この映画には、
大きな事件も、劇的な展開もありません。
あるのは、
親と子の間に生まれるわずかなズレや、
言葉にされない感情の積み重ねだけです。
しかし、その何気ない日常の中にこそ、
戦後を生きた世代の価値観や、
家族という関係の難しさ、
そして時代の変わり目に立つ人々の姿が、
静かに映し出されています。
子どもたちの態度に感じた、親との距離
東京で暮らす子どもたちは、
決して冷酷な人間として描かれているわけではありません。
長男も長女も、それぞれ家庭や仕事を持ち、
自分なりに懸命に生きています。
ただ、老夫婦を迎える態度からは、
どこか親との距離を感じずにはいられませんでした。
特に印象に残ったのは、
親を思いやる気持ちが「ない」のではなく、
「後回し」になっているように見えたことです。
東京での忙しい暮らしの中で、
合理性や効率が優先されるうちに、
親への真心の優先度が下がってしまった――
そんなふうにも感じました。
それは、誰にでも起こり得ることだと思います。
悪気がなくても、
日々の生活に追われているうちに、
大切な人への配慮が後景に退いてしまうことはあるからです。
また、長女の言葉から、
父親がかつて酒で母親を困らせていた過去が
さりげなく語られる場面もありました。
そのことから、
子どもたちはどこか父親に対して
距離を保っていたのかもしれません。
それが個人的な感情によるものなのか、
あるいは当時の家族関係や時代背景によるものなのか、
はっきりとはわかりません。
一方で、末娘の京子は、
兄や姉の親への態度に対して、
素直に落胆を示します。
その反応は、若さゆえの純粋さだったのかもしれませんし、
まだ親を「親」として必要としている年代だからこそ
感じ取れた違和感だったのかもしれません。
親の側もまた、
子どもたちに対して不満をぶつけることはありません。
穏やかに、静かに、
どこか諦観を含んだ態度で接します。
本音を語らないことが、
思いやりだった時代の空気も、
そこには漂っているように感じました。
子どもたちは親に甘えていたのか。
それとも、
自分たちの暮らしに余裕がなかっただけなのか。
親はそれをどこまでわかっていたのか。
この映画は、
そのどれにも明確な答えを出しません。
ただ、
親子であっても、
同じ気持ちを同じタイミングで分かち合えるとは限らない。
その現実を、静かに突きつけてくるようでした。
老夫婦の姿に映る、戦後世代の価値観
子どもたちとの間に、確かに距離はありました。
けれど老夫婦は、そのことを責めるような言葉を一切口にしません。
不満や寂しさを抱えていたとしても、
それを子どもたちにぶつけることはなく、
静かに受け止めているように見えました。
その姿から感じたのは、
戦後を生きた世代ならではの価値観です。
彼らは、思い通りにならない人生を
「そういうものだ」と受け入れることを
すでに身につけているようでした。
当時の日本では、
家族は一つの単位であり、
家制度の中でそれぞれに役割がありました。
個人の感情よりも、
立場や責任が優先される場面も多かったはずです。
礼儀や忍耐、我慢することも、
生きていくための知恵として教えられていた時代でした。
また、戦争という大きな喪失を経験した世代でもあります。
兄弟や仲間、
場合によっては自分の子どもを失った人も少なくなかった。
そうした耐え難い現実を生き抜く中で、
「言葉にしても仕方のないこと」を
胸の内に収める術を身につけていったのかもしれません。
だからこそ、老夫婦は、
子どもたちに多くを求めません。
自分たちの世代の価値観を押し付けることもなく、
ただ、今を生きる子どもたちの選択を
そのまま受け入れようとしているように見えました。
もしかすると、
戦争を経験し、我慢と忍耐の中で生きてきたからこそ、
自分の子どもには、
好きな人生を歩んでほしいと願っていたのかもしれません。
その結果、
子どもたちは確かに「自由」には生きている。
けれど、その自由な姿が、
親の目には必ずしも
「立派」に映らなかった部分もあったのではないでしょうか。
それでも老夫婦は、
人生は思い通りにならないものだと、
自分に言い聞かせるように、
穏やかに日常へ戻っていきます。
良いとか悪いとかではなく、
ただ、それぞれの世代が、
それぞれの時代を懸命に生きている。
そんな現実が、
この映画の静けさの中に浮かび上がってくるようでした。
紀子という存在が照らす「真心」
『東京物語』の中で、最も印象に残った人物は、
老夫婦の実の子どもたちではなく、
戦争で亡くなった次男の妻・紀子でした。
血のつながりはなく、
法的にも、すでに「家族」と呼ぶには曖昧な立場。
それでも紀子は、
義父母を気遣い、時間をつくり、
自然な距離感で寄り添おうとします。
その姿は、一見すると
「とてもできた人」「理想的な人」にも見えます。
けれど私は、
彼女の真心は、
決して清らかさだけで成り立っているものではないと感じました。
物語の終盤、
紀子は義父に対して、
本当は亡くなった夫のことを
忙しさの中で忘れかけている、と打ち明けます。
その告白は、とても正直で、
同時にとても人間的でした。
愛していたからこそ、
忘れてしまう自分を許せなかったのかもしれません。
前を向いて生きている自分に、
どこか負い目のような感情を抱いていたのかもしれない。
だからこそ、
義父母へのもてなしには、
夫への愛と、罪悪感と、
そして彼女自身の優しさが
静かに混ざり合っていたように思えました。
また、紀子にとって義父母との時間は、
亡き夫とのつながりを確かめる時間でもあったのではないでしょうか。
夫はもうこの世にいない。
けれど、夫を育てた両親は生きている。
その存在を大切にすることは、
夫の人生を否定しないための、
彼女なりの誠実さだったようにも感じます。
重要なのは、
紀子が「聖人」のような存在として描かれていないことです。
彼女にも迷いがあり、弱さがあり、
忘れてしまう人間としての現実があります。
それでも、
目の前の人に心を向けることを選び続ける。
その姿勢こそが、
この映画における「真心」なのだと思いました。
現代に生きる私たちにとって、
紀子のように振る舞うことは、
決して簡単ではありません。
自分の人生を守ること、
自分の時間や心の余裕を優先することが、
悪いことではない時代だからです。
それでも、
誰かの立場に立ち、
押し付けることなく、
態度で心を示すことはできる。
紀子の姿は、
そんな静かな可能性を、
私たちにそっと差し出しているように思えました。
語られない美しさとしての「所作」
『東京物語』を観て、もう一つ強く心に残ったのが、
女性たちの所作の美しさでした。
紀子や京子の動きは、とても静かで、控えめで、
決して目立つわけではないのに、自然と目が向いてしまいます。
言葉遣いだけでなく、立ち居振る舞いそのものに、
相手を思う気持ちがにじんでいるように感じました。
一方で、長女の所作はどこかせわしなく、
合理的で、少し棘のある印象も受けました。
善悪の問題ではなく、
所作にもその人の性格や生き方が表れるのだと、改めて感じさせられます。
特に印象的だったのは、
母の葬儀後、実家で家族が食卓を囲む場面です。
京子がご飯のおかわりをよそうとき、
お茶碗を直接手渡すのではなく、
おひつの横に置かれた小さなお盆に乗せて差し出す。
その何気ない動作が、とても美しく見えました。
礼儀や作法をきちんと学んでこなかった私には、
その所作が新鮮で、どこか懐かしく、
「こういう丁寧さを大切にして生きてみたい」と思わせる瞬間でした。
これは形だけのマナーではなく、
相手に対する敬意や、場を乱さない心遣いが、
自然と身体に染みついた結果なのだと思います。
語らなくても伝わる。
主張しなくても、相手を大切にしていることがわかる。
そうした日本独特の美意識が、
この映画の随所に静かに息づいているように感じました。
「混ざり合っている」という感覚
『東京物語』を観終えて、
強く残った感覚は、
誰もが善と悪をはっきり分けられる存在ではない、ということでした。
親を十分にもてなせなかった子どもたちも、
決して冷酷なわけではありません。
紀子の真心も、
純粋な善意だけで成り立っているわけではない。
そこには、愛情も、迷いも、罪悪感も、
いくつもの感情が静かに混ざり合っています。
それでも人は、
目の前の誰かに、
そっと心を向けることができる。
この映画は、
その可能性を否定しません。
誰かを断罪することも、
正解を提示することもなく、
ただ、そういう人間の姿があるのだと、
淡々と差し出してくる。
その姿勢自体が、
とても日本的で、
どこか宗教や思想を超えたもののようにも感じました。
善か悪か、
正しいか間違っているか、
白か黒か。
そうした二項対立では捉えきれない世界を、
『東京物語』は静かに描いています。
混ざり合っているからこそ、人は人間であり、
完全ではないからこそ、
誰かを思いやる余地が生まれる。
そのことに気づかせてくれる映画だったように思います。
それでも、静かに続いていく日常へ
『東京物語』は、
観終わったあとに大きな感動やカタルシスを与えてくれる映画ではありません。
けれど、時間が経つほどに、
じわじわと心の奥に残り続ける作品です。
親を大切にできなかった子どもたちも、
それを責めることなく受け入れる老夫婦も、
淡々と日常を生きる紀子も、
誰ひとりとして「正解」ではありません。
けれど同時に、
誰ひとりとして「間違い」でもない。
人は皆、
善と弱さ、思いやりと自己中心性を併せ持ちながら生きています。
その混ざり合った状態こそが、
人間の本質なのだと、
この映画は静かに教えてくれます。
禅や断捨離が大切にしているのも、
何かを完璧にすることではなく、
余計なものを削ぎ落とし、
「今ここ」に心を置くこと。
それは、紀子の生き方や、
小津作品に流れる静けさと、
どこか深くつながっています。
ドイツ人監督が、
この日本の古い映画に惹かれ、
そこから『パーフェクト・デイズ』という作品を生み出したことも、
とても象徴的です。
国や宗教、時代を超えて、
人が「静かに生きる」ということの価値は、
確かに伝わっていくのだと感じました。
私たちはつい、
もっと頑張らなければ、
もっと幸せにならなければと、
自分を追い立ててしまいます。
けれど『東京物語』は、
それでも日常は続いていく、
それでいいのだと、
そっと肩の力を抜かせてくれます。
完璧でなくても、
うまくできなくても、
それでも誰かを思う気持ちが、
ほんの少しでもあればいい。
そんな静かな肯定を胸に、
今日という一日を、
また淡々と生きていけたら。
『東京物語』は、
そう思わせてくれる映画でした。
この映画は、Amazonプライムで視聴しました。
プライム会員であれば、追加料金なしで観ることができます。