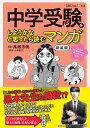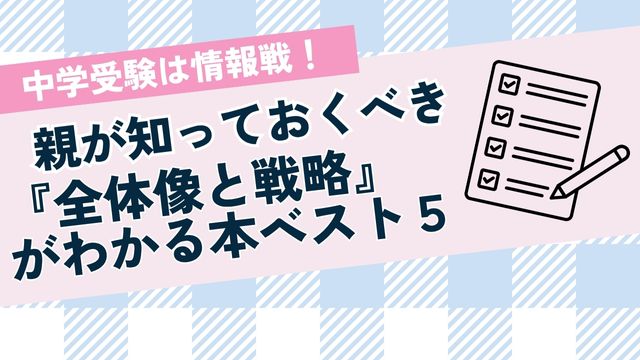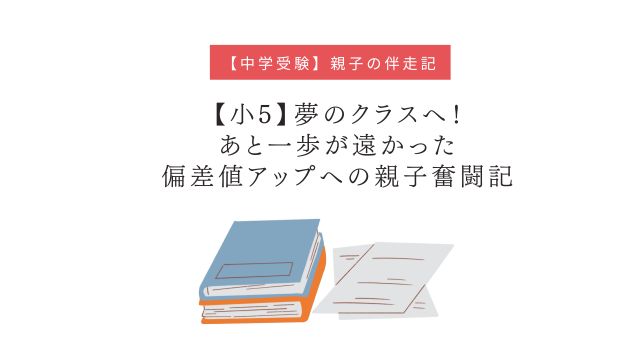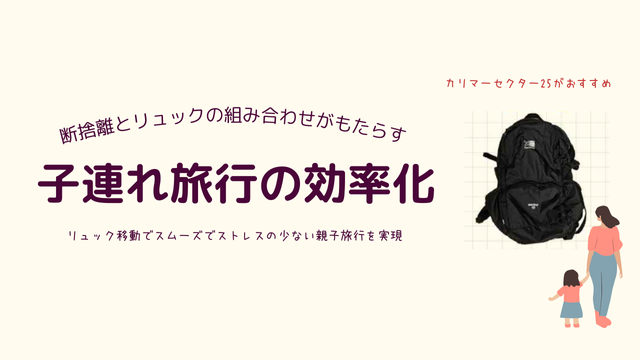【中学受験】親子の伴走記〜合格とその先にあるリアル中学受験〜<小4春>予想外の受験スタートと、親子の奮闘
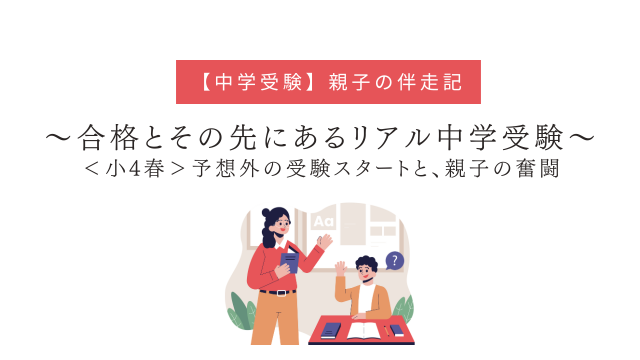
「中学受験、本当に大変だったけど、乗り越えてよかった!」
今、娘は中学1年生。バスを乗り継ぎ、念願の第一志望校である私立中学に通っています。
正直に言うと、中学受験は親子にとって、想像を絶するほど「きつかった」というのが本音です。
この経験を、私自身の備忘録として。
そして、これから中学受験を考えている方、塾選びで悩んでいる方のリアルな参考になればと思い、中学受験体験記をシリーズでお届けすることにしました。
このブログを通して、中学受験の「リアル」を知っていただき、あなたのご家庭にとって本当に中学受験が必要かどうか、その判断の一助となれば幸いです。
「そもそも、なぜ、わが家は中学受験を選んだのか?」
中学受験を終え、娘との長い道のりを振り返る今だからこそ話せる、その始まり。
すべては、漠然とした不安と、目の前の子どもの変化からでした。
あの日々を鮮明に思い出しながら、これから中学受験を検討する親御さん、そしてまさに今、同じような悩みを抱えている皆さんの心に寄り添い、私たちのリアルな体験をお伝えしていきます。
今回は、わが家が中学受験を目指すことになった経緯や、小学4年生の序盤の様子をお話しします。
活発だった娘が変わった?小学校生活の始まりと「校区問題」

保育園の頃の娘は、本当に活発で、友達の輪の中心にいるような子でした。誰とでもすぐに仲良くなり、外で元気に遊ぶ姿を見て、私たちは何の心配もしていませんでした。
しかし、小学校入学と同時に、一番仲の良かった友達が遠くへ引っ越してしまったのが、娘に大きな影響を与えたのかもしれません。小学校に進学してからは、放課後に友達と遊ぶこともなくなり、どこか消極的な印象を受けるようになりました。
保育園の年長さんから、小学校の生活に慣れるためにもと、学研に通わせていました。
椅子に座って学習する習慣をつけるのが目的です。
ところが、小学校に入学すると、学研の宿題と学校の宿題、両方に慣れるのが大変だったようで、小学1年生の頃は、毎日泣きながら宿題に取り組む日々でした。
私も「宿題は親が見てやるべきもの」「きちんとやらせなければ」という思いが強く、仕事から帰ってきて必死に娘と向き合っていました。(今思えば、かわいそうなことをしたと猛省しています)
そんな小学2年生の頃、コロナ禍で学校がオンライン授業に。自宅で過ごす時間が増えたことで、暇つぶし対策として我が家ではYouTubeが解禁されました。これが、その後の娘の生活に大きな変化をもたらすことになります。
学校が再開しても、クラスの子たちとは関わるものの、放課後に誰かと遊びに行くことはありませんでした。
学童にも通っていましたが、学年が違う縦割りのグループに馴染めず、高圧的な態度の高学年の男の子がいるグループでは怯えてしまい、学童を嫌がるように。
結局、2年生の夏休み後には学童をやめることになりました。
学童やめたあとは、母にお迎えや留守番をお願いすることも多くなりました。
保育園であんなに積極的に友達と遊んでいた娘が、家ではYouTubeを見たり、絵を描いたり、一人で静かに過ごす時間を楽しんでいる様子。
活発だった娘の様子が明らかに変わったので、私たち親は、漠然とした心配を抱え始めていました。
小学3年生になっても、状況は特に変わりません。
クラスには仲の良い友達はいるものの、放課後はまっすぐ帰宅してYouTube三昧の日々。
さらに、追い打ちをかけたのが「校区問題」です。
我が家の校区の中学校は、同じマンションの方やご近所さんからも「評判が悪い」「いじめもあるらしい」とよく耳にする場所でした。
中学受験をしたお宅や中学だけわざわざ引っ越して校区を変えたお宅もあったと聞き不安になってきました。
消極的になっていた娘が、そんな環境で楽しく過ごせるのか。
友達に合わせるタイプなので、付き合う友達によっては悪い影響を受けるのではないか。親として、不安が募るばかりでした。
「なんとなく」から始まった中学受験への道

娘の性格の変化と、校区への不安が重なり、以前から頭の片隅にあった「中学受験」が、具体的な選択肢として浮上してきました。
まずは情報収集…となるはずが、そこは「なんとなく」で進んでしまうのが我が家。
学研の先生に相談してみると「5年生くらいからでも大丈夫ですよー」と言われたので、先生を信頼し深く調べもせず、その言葉を鵜呑みにしてそのまま過ごしていました。(この先生の情報が、実は以前の中学受験の常識だったことが後からわかるのです)
そして、娘が小学4年生になる春休み。新年度から中学受験の塾に切り替えようと、軽い気持ちで中学受験専門塾の門を叩きました。
しかし、そこで現実を突きつけられます。
「現在の中学受験は、小学3年生の3学期からが慣例」だということ。
すでに春期講習からスタートした娘は、他の子たちよりも少し遅れた状態での開始となりました。
たったそれだけのことなのに、テキストには習っていないところがたくさん出てくる…!
私も塾のカリキュラムや宿題の多さに驚き、家で必死に調べながら、教えながら、娘と一緒に宿題をこなす日々が始まりました。
娘も、いきなりの勉強量の増加と、塾のクラスメイトについていけないことが苦しくて、泣きながら宿題に取り組むようになりました。
私も「塾で言われたことは守らなければいけない」「どんなことをしてでも宿題を終わらせなければ」という義務感で必死でした。
毎晩、塾の宿題には私がつきっきり。親子で文字通り、泣きながら机に向かう時間が続きました。
まだ4年生だからと、少し気が緩んだ部分もあり、時々はお出かけもしました。
季節ごとの集中講座も、5年生や6年生に比べれば日数も宿題も少なかったので、少し遊びの日も設けつつ、塾中心の生活が始まりました。
娘が最初に入った塾のクラスは、下から2番目(5段階中下から2番目。上位3クラスは週テストやマンスリーテストなどで常にクラス変動あり)のクラスでした。
このクラスは、まず中学受験の基本的な知識や解き方をしっかりと身につける段階、という位置づけです。
4年生の頃は、週テストもあるものの、マンスリーテストで理解度を確認する形でした。上のクラスは週テストもあり、マンスリーテストごとにクラスが変動していました。
大手塾の現実・・・クラス格差と費用負担

中学受験で有名な大手塾に通うことにしました。
職場の先輩の娘さんが東大を受験するほどの実力の持ち主で、中学はトップ校に通っていたそう。その娘さんが通っていた塾や、周りの話、私立小学校に通っているママ友の情報を頼りに、「中学受験といえばここ」という大手の塾を選んだのです。
入塾して感じたのは、上位クラスの子たちとの待遇の差でした。娘のいた下位クラスでは、先生もそこまで手厚くなく、テストの結果だけを見て、「ひとまずクラスアップを目指しましょう」というアドバイス程度でした。
先輩の話では、先輩の娘さんは塾の上位クラスのトップだったので、塾代もある程度免除されていたそうです。
算数オリンピックにも参加していたと聞きました。
東大合格への可能性がある子には、塾で一番優秀な先生が担当についているようでした。娘さんは後に東大は不合格でしたが、国立大(旧帝国大)に合格し、現在は文部科学省にお勤めです。
正直、上位クラスの子たちの塾代は、下位クラスの私たちが担っているんだな、と感じました。(これも、全国の大手塾では「あるある」だと、本やネットの情報で後から知ることになります。)
集団塾でついていけない子は、割高な個別クラスを追加で受講するように勧められますし、それでも無理な子は家庭教師に切り替える家庭もあるようです。
4年生で体験した、オープンキャンパス巡りの日々

この1年間は、いくつかの学校のオープンキャンパスにも足を運びました。主に夏に開催されるものですが、本当にたくさんの学校を見て回りました。
我が家は校区の問題と娘の消極的な性格を心配しての中学受験だったので、なるべく娘の行きたい学校へ行ってほしいと思っていました。
偏差値が高い人気校は、ただの見学と受験対策の説明が主でした。一方で、偏差値が高い人気校を除く多くの学校では、生徒が学校の良さを発表したり、英語のスピーチを披露したりと、学校側も手厚い「おもてなし」感がありました。入試対策や個別相談なども充実していて、とても参考になりました。
「偏差値が低いからダメ」ではない。偏差値が低くても、豊富な指定校推薦枠があったり、学校独自の魅力があったり、子どもの性格に向いている学校はきっとある。
そう信じて、気になる学校はすべてオープンキャンパスで見て周りました。
オープンキャンパスはたいてい土曜日の午前中に開催され、塾が午後2時から始まるため、土曜日の娘のスケジュールは非常にタイトでした。
ちなみに、私が住んでいるのは5大都市の一つである地方都市です。
東京や大阪よりも中学受験に取り組む子どもの数は少ないものの、塾での学習の進め方や私立中学のカリキュラムなどは都心の私立中学とほぼ同じです。
都心に比べて私立中学の学校数が少ないのが現状で、まだまだ公立トップ校の方が若干人気があるように感じます。
しかし、私立中学は豊富な推薦枠があるのが大きなメリットの一つだと改めて感じました。
一人っ子の娘が伸び伸びと過ごせるように、共学の学校が良いなと漠然と考えていたので、女子校は全く眼中にはありませんでした。(女子校の良さを6年生になって知ることになります。)
4年生の間は新しい知識を習得していき、基本問題ができれば発展問題に進む子もいますが(上位クラス)、わが家はとりあえず基本問題が7割以上できていたので、大変ながらも東大を目指しているわけではないからと、比較的のんびりと、塾の言われた通りに進めていた感じでした。
この時点では、まだ中学受験の道のりが、これほどまでに長く、そして深いものになるとは想像もしていませんでした。
次回は、小学5年生になり、いよいよ本格化する中学受験の「中だるみ」と、クラスアップを目指して奮闘する親子の葛藤についてお話ししたいと思います。どうぞお楽しみに!
この本は、中学受験のリアルなので絶対に読んで損はないです。
こちらも、絶対に読んでほしい漫画です。めちゃリアル。過去にドラマにもなっていますが、塾のシステムも理解できますし、いろんなお子さんのパターンが見れるので、とても参考になります。何度読んでも泣ける。。。
こちらは実体験の3家族のお話です。オーディオブックで何度も聴き、涙しました。
2月の勝者のリアル版です。なので、2月の勝者を読んでもらえばまんまリアルな中学受験を知れます。
ここでは、おすすめの教材はありません。
大手塾に通われるなら、塾の教材で十分です。
むしろ、あれもこれも手を出さずに愚直に塾のオリジナル教材を繰り返せば必ず、絶対に合格します(膨大な量をこなせるかが問題)
それくらい、塾の教材は練りに練られた最高の教材です。
これについても、2月の勝者で読んでもらえばわかると思います。

私の体験記がお役に立てれば、嬉しい限りです!
中学受験ママ、頑張ってくださいねー!